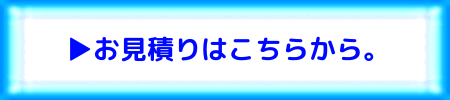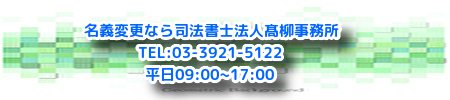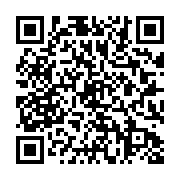一般社団法人設立
設立登記においては設立する方の代理人となれるのは司法書士と弁護士のみです。
もちろんご自身でも設立登記は可能です。
ただ全てに掛かる費用に司法書士と個人では大差がないのはご存知ですか?
ご自身の仕事に素早く対応し専念する為にも専門家である
司法書士にお任せ頂ければと思います!
一般社団法人設立の費用(料金)の目安
| 一般社団法人設立費用(料金) 182,000円~ |
| 項目 | 報酬(料金) | 実費 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料(公証人手数料) | 0円 | 52,000円 |
| 登録免許税 | 0円 | 60,000円 |
| 報酬(料金)目安 | 70,000円~ |
一般社団法人設立登記・手続きの流れ
| ●ご依頼者様に安心して頂くために。。 |
| (担当の司法書士を含めアシスタント1~2名にて専属で対応致します。) |
 |
| 打ち合せ |
|---|
| お電話もしくは面談のご予約をお願い致します。一般社団法人設立についてご説明させていただきます。 |
| 来所が厳しい方は担当にご相談ください。 |
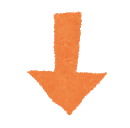 |
| 商号調査 ・法人印鑑のご用意 |
|---|
| 法人の名称が同一住所にないかチェックを致します。 |
| 法人の印鑑をご用意いただきます。 |
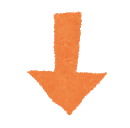 |
| 定款の作成 |
|---|
| ご依頼者様と内容の確認を進めながら定款を作成いたします。 |
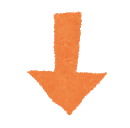 |
| 定款認証 |
|---|
| ご依頼者様に委任状へ押印して頂きます。公証役場にて定款認証致します。 |
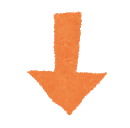 |
| 登記申請書を作成 |
|---|
| 設立登記に必要な書類を作成いたします。 ご依頼者様にご捺印頂きます。(実印にて) |
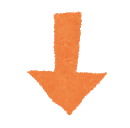 |
| 設立の登記を申請する(法人設立) オンライン申請 |
|---|
| 登記の申請を致します。申請をする日が設立日となります。大安をご希望の方は登記の申請日の調整をさせて頂きます。 |
| 申請はオンラインとなります。事務所より全国の申請が可能となります。 |
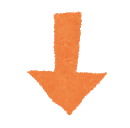 |
| 登記完了・お支払い |
|---|
| 登記申請後、1週間~10日ほどにて登記が完了致します。 |
| 一般社団法人とは? |
|---|
| 一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。 |
| 一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。一般社団法人の特徴としては「持分の定めのない法人」であることです。 |
| 株式会社とは異なり出資者が存在しないということになります。 |
| 非営利の法人である |
|---|
| 一般社団法人は、非営利の法人です。「非営利」とは営利を目的としないことです。 |
| では、そもそも「営利」とは何かと言えば、構成員に剰余金を分配することです。 |
| 株式会社の場合、生じた利益は株主に分配(配当)されます。株式会社は、剰余金を分配するための法人なので営利法人です。 |
| その反対の意味で、剰余金を構成員に分配しないことを、法律上の概念では「非営利」と言います。 |
| つまり、一般社団法人は、構成員に剰余金を分配しないという意味で非営利の法人です。 |
| 誤解している方も多いのですが、法律上の「非営利」とは、利益を上げてはいけないとか、お金を儲けてはいけないとか、そのような意味ではないのです。 |
| 一般社団法人は、しっかり売上を上げて、しっかりお金を儲けていいのです。 |
| ただし、生じた利益を「剰余金の分配」という形で、社員や理事に分配してはいけないという制度です。 |
| 生じた利益は「剰余金の分配」ではなく、次の事業の再投資に回すことになります。 |
| なお、一般社団法人が雇用している従業員に給料を払ったり、理事に役員報酬を払うことは、問題なく可能です。 |
| 税制上の優遇がある【非営利型の場合】 |
|---|
| 一般社団法人は、設立の仕方によって、収益事業のみが課税となる「非営利型」としての設立が可能です。 |
| 「非営利型」の場合、NPO法人と同じ税制ですので、非営利型の一般社団法人には会費収入には課税されないことになります。 |
| 事業内容に制限がない |
|---|
| 一般社社団法人は、とくに目的や事業内容について法律上の制限がありません。どのような事業内容であっても適法である限り、自由です。 |
| そのため、法人格を得て活動したい団体にとっては便利な制度です。 |
| 設立期間が比較的短い |
|---|
| 一般社団法人は、株式会社等と同様に、公証役場の定款認証と法務局の登記だけで設立可能です。 |
| 期間としては、早ければ数週間程度でも法人設立が可能です。 |
| 設立時に出資は不要 |
|---|
| 一般社団法人には、会社のように「資本金」という概念はありません。 |
| その分、資金が少ない団体でも法人設立が可能です。 |
| ちなみに一般財団法人の設立には、最低300万円の拠出金が必要ですが、そのような規制は一般社団法人にはありません。 |
| 設立に際して、最低2名から |
|---|
| 一般社団法人の機関設計のパターンは、以下の5通りです。 |
1.社員総会+理事 (社員とは社員総会にて決議権を持つ者となります) 2.社員総会+理事+監事 (社員は理事・監事になることができますが兼任はできません) 3.社員総会+理事+監事+会計監査人 4.社員総会+理事+理事会+監事 5.社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人 |
| 設立時に最低社員2名以上が必要です。 |
| 1名を理事(社員と理事の兼任は可能)とし、もう1名が社員となり最低2名より設立が可能となります。(1.適用) |
| 基金による資金調達が可能 |
|---|
| 基金とは、一般社団法人だけに認められた独自の資金調達方法です。 |
| 「基金」は、寄付金や、通常の借入金とも異なる資金調達方法です。 |
| この基金について、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、法人の活動原資として自由に使うことができます。 |
| 一般社団法人は剰余金の分配が禁止された非営利組織であることから、寄付したからと言って見返りがあるわけではありません。 |
| このため、寄付や借り入れ金以外にも、使途の制限が無い法人の活動原資となるような資金調達が必要とされます。 |
| それのために基金制度が設けられています。 |
| 監督官庁がないので活動が自由 |
|---|
| 一般社団法人には、監督官庁が存在しないため、活動は一切自由です。 |
| 一般社団法人と株式会社の税金の比較 |
|---|
| 株式会社と普通型一般社団法人は、全ての定款の所得が課税対象となります。 |
| 非営利型一般社団法人は、収益事業、収益事業外と会計を2つに分け、収益事業から生じた所得のみが課税の対象となります。 |
| すなわち収益事業外は非課税というわけです。 |
| ●一般社団法人👉利益は分配できない。次年度以降の事業拡大のために使用。収益事業を分けることにより課税対象金額が変わる。 |
| ● 株式会社 👉利益を株主へ分配する。所得は全て課税対象となる。 |
| ※税理士の顧問契約等ご希望によりご紹介いたします。 |